GOST-Rとは
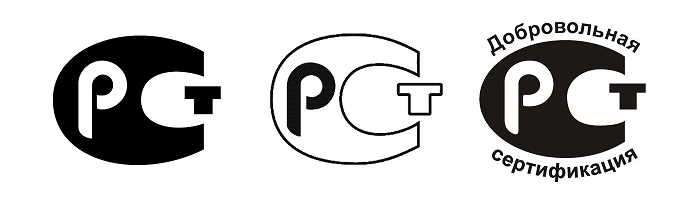
EAC認証導入前からロシアと取引をしていた方や、EAC認証導入前にロシアと取引をした経験をお持ちの方は、ロシアの認証=GOST-Rという認識が強く、GOST-R認証とEAC認証の違いについてよくお問い合わせいただきます。
また、ネット上では「GOST-Rは廃止されました」という情報も散見されます。
そもそもGOST-Rというのは、ロシア国内規格(GOvernment STandard of Russia)のことで、日本独自の規格であるJISやJASと同じものです。GOST-R自体はなくなっているどころか、新しいGOST-Rは毎月沢山作成されています。
技術規制に関する連邦法(2002年12月27日付 N 184-FZ)によって、「規格は自主的に適用するものであってその存在自体が強制力を持つものではない」という規格の自主性が明文化されたことで、ロシア市場に向けて出荷される製品に「GOST-R(規格)への適合を強制する制度」が「TR (技術規則)への適合を強制する制度」に変わっていったのです。そして、TRはロシア国内法規からユーラシア経済連合(前身は関税同盟)共通法規へとかわり、現在のEAC認証に至るわけです。
強制認証としてのGOST-R
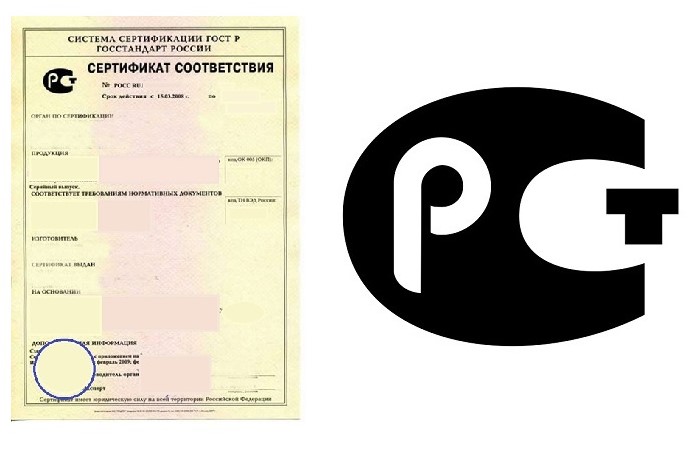
EAC認証の始まりとして2012年2月15日にTR CU 006/2011「火工品の安全性について」が施行されてから8年が経過し、ロシアを含むユーラシア経済連合市場で流通する製品の多くがEAC認証制度の下、適合宣言書、適合証明書、国家登録証明書などを規制している規則の規定に従って取得しています。
ロシアはユーラシア経済連合の加盟国なので、施行済みの関税同盟技術規則(TR CU)又はユーラシア経済連合技術規則(TR EAEU)の規制対象となっている場合、EAC認証制度での適合宣言書、適合証明書の取得が必要となります(国家登録の対象製品についてはここでは言及しません)
しかしながら、消費者の安全等を考えた場合、安全性を強制的に確認すべきである製品なのにTR CUやTR EAEUがまだ採択されていない場合、GOST-Rへの適合を強制する制度を一律に廃止してしまうと不都合が生じます。
そこで、ロシア政府によって2009年12月1日「適合証明書および適合宣言書の取得が義務である製品のリスト(政令No.982)」が承認され、このリストに含まれる製品については、GOST-R制度に基づく証明書の取得が義務付けられていることがわかるようになったのです。
政令No.982のリストに記載されている製品は、その製品を規制するTR CU (EAEU)が採択されるとリストから削除されます。現在ではかなり短いリストになりました。
2021年12月23日付ロシア連邦政府命令No.2425「強制認証対象製品一覧及び適合宣言対象製品一覧、2020年12月31日付ロシア連邦政府命令への変更及びロシア連邦政府のいくつかの法令の廃止について」(政令No.2425)によって、政令No.982が廃止され、新しいリストが採択されました。
政令No.2425によって承認されたロシア国内制度での強制認証・適合宣言対象製品一覧は、これまで複数の法令にまたがって規定されていた適合規格、HSコードがすべて一目でわかるようになっています。そのため、出荷予定の製品がEAC認証の対象ではない場合、ロシア国内では強制認証・適合宣言の対象となるのかどうか、対象である場合はどうしたらいいのか、というのはこの法令を参照するだけで足ります。
強制認証で26品目、適合宣言で67品目が、対象となっています。
リスト詳細についてはこちらをご確認ください。
EAC認証の対象ではなくても、ロシア国内に出荷する製品の場合、政令No.982のリストに記載がある場合はGOST-Rの適合宣言書又は適合証明書が必要となり、それに伴いGOST-Rマークの貼り付け義務もありますので注意が必要です。
自主認証としてのGOST-R
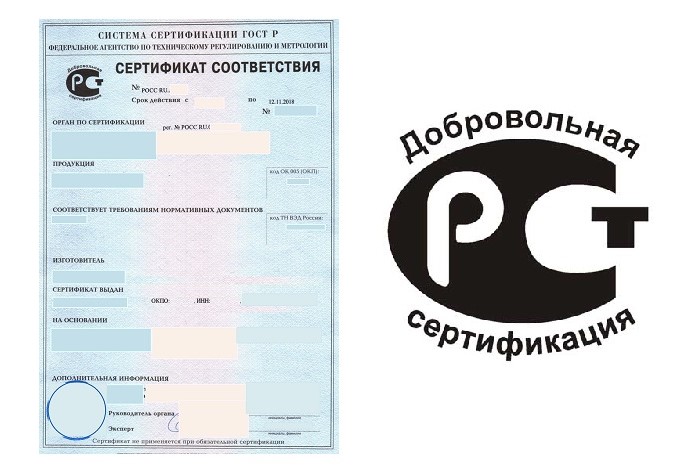
何らかのGOST-Rに適合していることを証明することで商品の価値をあげることができる場合、自主認証としてGOST-Rを取得することもできます。
あくまで製品PRのためのものなので、「通関対策に自主認証をとりましょう」という見解に弊所は懐疑的ですし、無意味だと思っています。
施行済みのいずれかのTR CU(EAEU)の対象ではない、政令No.982のリストにも記載されていない製品である場合、胸を張って通関を切ってください。どうしても不安がある場合、認証機関に「非該当レター」(Refusal Letter)を書いてもらってもいいと思います。
GOST-R認証の取得方法についてご質問がありましたらお問い合わせください。




